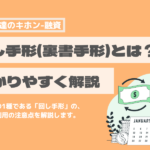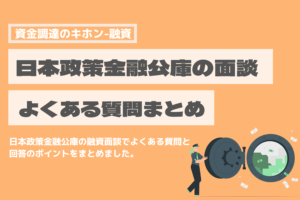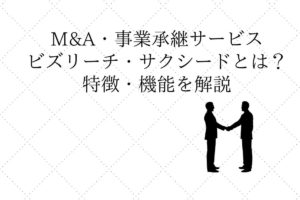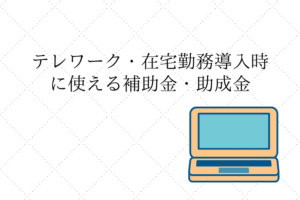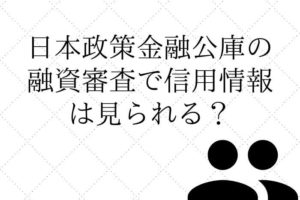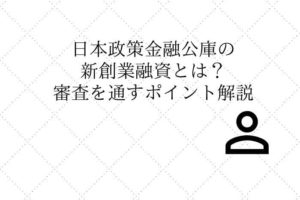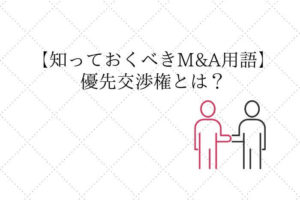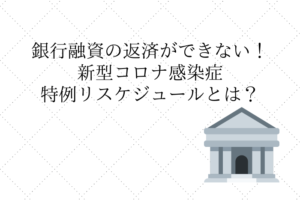「資金繰りが厳しくて、日本政策金融公庫の返済ができそうにない…」
そんな不安を抱えている経営者の方は、決して少なくありません。
実際、売上の遅れや入金タイミングのズレなど、ちょっとしたキャッシュフローの悪化が原因で、返済が難しくなることは誰にでも起こり得ます。
だからといって、連絡をしないまま放置してしまうと、状況はどんどん悪化してしまう恐れがあります。
公庫からの督促、最悪の場合は一括請求や資産の差し押さえといったリスクに発展することも。
本記事では、そんなピンチの時に知っておきたい:
- 公庫からの督促の流れ
- 今すぐできる3つの現実的な対処法
- 倒産や破産を避けるための知識や相談先
をわかりやすく解説します。
「返済できない=終わり」ではありません。
早めの行動こそが、事業継続のカギです。
最悪の事態を防ぐために、今できる一歩から一緒に始めましょう。
返済できないとどうなる?日本政策金融公庫の督促・回収の流れ
「返済が遅れてしまったら、どうなるのだろう?」
日本政策金融公庫から融資を受けている中小企業や個人事業主の方にとって、最も不安になる場面のひとつではないでしょうか。
ここでは、返済が滞った場合の公庫側の対応の流れと、それにどう向き合うべきかを解説します。
早めの相談・対応をすれば、回避できる段階もあります。
ステップ①:担当者からの電話督促(滞納2〜3日目)
まず最初にあるのは、公庫担当者からの電話による確認連絡です。
この段階では、返済の意思があるかどうか、支払い予定日が伝えられるかが重要です。
無視せず、正直に事情を説明することで返済猶予や分割の相談に応じてもらえることもあります。
ステップ②:督促状が郵送で届く
電話での連絡でも解決しない場合、「督促状」が書面で届きます。
この書面には、滞納金額、支払期限、遅延損害金などの詳細が記載されています。
この時点でもまだ、支払い意思を示し連絡を入れれば柔軟に対応してもらえる余地があります。
ステップ③:一括請求書の送付(滞納2〜3か月目)
滞納が続くと、借入金の全額返済を求める「一括請求書」が届きます。
元本・利息・遅延損害金をすべて即時支払うよう求められるため、経営に大きな打撃を与える可能性も。
ここまで来る前に、必ず公庫へ連絡を入れることが大切です。
ステップ④:債権回収会社(サービサー)への移管または代位弁済
さらに対応がされないまま放置されると、債権が第三者(サービサー)に譲渡されるか、信用保証協会により代位弁済が実行されます。
この段階では、法的手続きを前提とした対応が進められ、資産の調査や差し押さえが視野に入ってきます。
ステップ⑤:訴訟・差し押さえのリスク(最終段階)
最終的には、裁判所からの訴状が届き、法的手続き(訴訟)に発展するケースもあります。
裁判で債務者側が敗訴すると、預金・売掛金・不動産などの差し押さえ=強制執行が行われる可能性があります。
ただし、そこまで至る前に交渉の余地は十分にあります。
「返済できない」と感じた時点で、早期に相談することが最善の防止策です。
日本政策金融公庫に返済できない時の3つの対処法
返済が遅れそうなとき、「どうしよう…」と焦ってしまうのは当然のことです。
しかし、そのまま放置してしまうと、督促や一括請求などのリスクが一気に高まります。
大切なのは、“今できる対処”を早めに行動に移すこと。
ここでは、日本政策金融公庫に返済できないときの現実的な3つの対処法をご紹介します。
対処法①:公庫の担当者に「返済猶予」の相談をする
まず検討したいのが、日本政策金融公庫の担当者に連絡を取り、「一時的に返済を待ってもらえないか」相談する方法です。
実際、公庫側も「返済できずに倒産する」より、「一時的に猶予してでも事業を立て直してもらう」方を望んでいます。
- 資金繰りが一時的に厳しい場合
- 来月以降の入金見込みがある場合
このようなケースでは、返済期限の延長や返済額の調整などに応じてもらえる可能性があります。
※ただし、猶予が必ず認められるとは限りません。早めに事情を丁寧に説明することが重要です。
対処法②:リスケジュール(返済条件の変更)を申し込む
返済の遅れが一時的なものではなく、経営全体の見直しが必要な状況であれば、「リスケジュール(条件変更)」の検討が必要です。
リスケジュールとは:
- 毎月の返済を一定期間利息のみにしてもらう
- 月々の返済額を減額してもらう など
本格的に資金繰りを改善する時間を確保することができる一方で、新たな借入が難しくなるデメリットもあるため、メリット・デメリットをよく比較してから申請を行いましょう。
【関連記事】リスケジュールのメリット・デメリット!成功率はどれ位?
対処法③:つなぎ資金を調達して一時的にしのぐ
「返済の遅れは一時的で、来月の入金があれば持ち直せる」
そんな場合は、返済原資を確保するための短期的な資金調達も選択肢の一つです。
スピード重視の資金調達方法としては:
- ファクタリング(売掛金の早期現金化)
- ビジネスローン(審査スピードが早い) など
特にファクタリングは、赤字・債務超過でも利用できる可能性があり、審査も比較的柔軟です。
【関連記事】ファクタリングとは?仕組みと活用方法をわかりやすく解説
【関連記事】赤字や債務超過中でも資金調達できる6つの方法
まずは「放置しない」ことが最も大切です
返済できない場合は、放置せず、早めに相談・行動することで選択肢は確実に広がります。
- 返済猶予の相談は、1日でも早く
- 中長期的に苦しい場合は、リスケの検討を
- 一時的なつなぎであれば、資金調達も有効
自社の状況に合わせて、今できることから始めましょう。
日本政策金融公庫のリスケ対応事情|断られる不安がある方へ
「リスケジュール(条件変更)って、実際に応じてもらえるの?」
こうした不安から、相談をためらってしまう経営者の方は少なくありません。
しかし実際には、日本政策金融公庫は政府系金融機関として、返済に困った中小企業・個人事業主に対して比較的柔軟に対応してくれるケースが多くあります。
過去には年間8万件以上の条件変更実績も
少し前のデータにはなりますが、平成20年度には年間約8万件の条件変更(リスケ)実績がありました。
この数字は、リーマンショック後の経済的混乱の中で、多くの中小企業を救済する対応をとっていたことを示すものです。
現在も、個別の状況に応じて:
- 一時的に返済をストップ(元本据置)
- 返済額を軽減
- 返済期間の延長
などのリスケ対応を行っている例が多数あります。
リスケ相談は“特別なこと”ではありません
リスケというと、「経営が危ないと判断されるのでは…」「次の融資が受けられなくなるのでは…」と心配される方も多いですが、公庫は“倒産させないこと”を優先しています。
そのため、一定の資料(試算表・返済計画など)を準備し、早めに相談すれば、門前払いされるようなことは基本的にありません。
※ただし、新たな融資が難しくなるなどの影響もあり得るため、リスケのメリット・デメリットはよく理解しておきましょう。
倒産した場合、代表者も自己破産する必要があるのか?
会社が倒産しても、代表者まで自己破産しなければいけないのか?
これは多くの経営者が不安に感じる、非常に重要なポイントです。
ここでは、「自己破産の必要がある場合・ない場合」をパターン別に整理してご紹介します。
結論:無担保・無保証であれば、自己破産が不要なケースもある
日本政策金融公庫の融資のうち、以下の制度を利用している場合、原則として代表者が自己破産する必要はありません。
これらは、無担保・無保証人での融資制度です。
また、法人(株式会社など)と代表者個人は法律上は別人格とされるため、会社の債務=代表者の債務とは限りません。
つまり、法人が倒産しても、代表者個人に保証がついていなければ、自己破産をしなくて済む可能性があるのです。
ただし、以下のケースでは代表者も責任を負う可能性あり
一方で、以下のいずれかに該当する場合は、法人が倒産しても代表者が債務を引き継ぐ可能性があるため、自己破産の検討が必要になります。
- 代表者保証付きで借入していた場合
- 個人事業主として日本政策金融公庫から借入していた場合
- フリーランスや副業個人での借入
- 法人名義でも、代表者が連帯保証人になっている場合
このようなケースでは、会社が倒れても債務は代表者個人に残るため、放置すれば個人の差し押さえ・信用事故につながるリスクもあります。
自分がどの融資制度を使っているか確認するには?
- 借入時の契約書・保証書の有無
- 公庫の融資制度名(借入内容通知書に記載)
- 公庫の担当者に**「代表者保証の有無」「返済義務の範囲」**を確認するのが確実です。
「会社が潰れた=すぐに自己破産」と決めつける必要はありません。
まずはご自身の契約内容を確認し、落ち着いて対応していきましょう。
緊急の場合は、つなぎ資金を調達して乗り切るのも一つの手
ここまで、日本政策金融公庫への返済が難しくなったときの対処法についてご紹介してきました。
とはいえ、
- 「今月だけ一時的に資金が足りない」
- 「入金の遅れで、返済日までにお金が用意できない」
といったケースもあるでしょう。
そんなときは、「つなぎ資金」を活用して乗り切るという方法も有効です。
つなぎ資金として使える手段とは?
短期的な資金確保を目的とした調達方法としては、次のような手段があります。
- ビジネスローン(銀行やノンバンクなど):審査スピードが早く、即日融資に対応する業者も存在
- ファクタリング(売掛金を現金化):売掛金があれば、赤字や債務超過の企業でも利用できる可能性あり
これらの手段は、公庫の返済日までの“つなぎ”として活用しやすく、資金ショートを回避する緊急策として選ばれています。
一人で抱え込まず、相談機関も活用を
「どう動けばいいかわからない」「自社にどの方法が合っているか判断できない」
そんなときは、以下のような相談窓口を活用しましょう。
-
日本政策金融公庫の担当者
→ 条件変更(リスケ)や相談記録を取ってもらえる -
税理士・会計士などの専門家
→ 経営状況に基づいた最適な資金繰り提案を受けられる -
商工会議所や認定支援機関
→ 無料で資金繰り改善のアドバイスを受けられる場合も
「誰にも相談できないまま放置すること」が、最も大きなリスクです。
- つなぎ資金の活用で、ピンチをしのげるケースは多い
- 早めに行動すれば、選べる選択肢も増える
- 状況に応じて、リスケ・資金調達・専門家相談を柔軟に使い分けることが重要
一歩踏み出すだけで、道が開ける可能性は大いにあります。
今こそ、状況を整理し、「できること」から始めてみてください。